
和太鼓
日本伝統の音で
響き合う音と心

和太鼓の活動では、音を出す楽しさや、友だちと音を合わせる気持ちよさを体いっぱいに感じることができます。
ただ演奏を「見せるため」ではなく、子どもたち自身の「みんなで演奏を完成させたい」という気持ちと、「そこに至るまでの過程」を何より大切にしています。
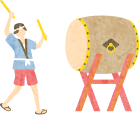
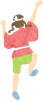

子どもが主体となって取り組む
加茂川保育園の和太鼓活動では、子どもが「年長さんみたいに太鼓を叩いてみたい」「音を感じてみたい」「友だちと一緒にやってみたい」と思う気持ちから始まります。そんな、興味や好奇心から自然に参加したくなるような雰囲気づくりを大切にしています。

仲間とつながる喜びを感じる
太鼓は一人で叩くのではなく、みんなで音をそろえる「合奏」です。自分の音、友だちの音、それが重なってひとつになる楽しさの中で、子どもたちは自然と「人の話を聴く力」「順番を待つ力」「合わせる工夫」などを学んでいきます。

※和太鼓は、「音研」からの専門の講師とともに活動にあたっています

リズム運動
「こころ」と「からだ」が
動き出す、リズムの時間
加茂川保育園では、子どもたちの発達を支える多様な活動を取り入れています。
その中でも、リズム運動は、体を動かす楽しさだけでなく、子どもたちの心と体の発達を支えます。





感覚を育み、身体を調整する(感覚統合の視点から)
リズム運動では、跳ぶ・転がる・這う・回るなど、全身を使った多様な動きをします。これらの動きは、子どもたちが視覚(見る)、聴覚(聞く)、触覚(感じる)、平衡感覚(バランス)など、複数の感覚を統合しながら動く=感覚統合を育てます。この力が高まることで、姿勢の安定や動作の調整がうまくできるようになります。

仲間と一緒に動くことで育つ(協働性・社会性)
音楽に合わせて、みんなで体を動かすことは、「同じリズムを感じる」「呼吸を合わせる」といった体験につながります。この中で、子どもたちは自然と「相手を意識する力」や「協調性」を身につけていきます。上手・下手ではなく、「みんなと一緒に楽しめた」という経験が、他者と関わる喜びや自信へとつながります。


運動遊び
“遊び”が“挑戦”に変わる
瞬間がやってくる
加茂川保育園では、多様な方法で「運動遊び」を取り入れています。
子どもたちは遊びの中で、「走る・登る・転がる・ぶら下がる・飛ぶ・渡る」という、乳幼児期に大切な6つの基本的な動きを満たしていきます。いつの日か、それが 遊びから挑戦へ と変わる瞬間が訪れます。保育者はその成長の過程を丁寧に見守り、子どもたちに寄り添います。
※当園の運動遊びは、安田祐治氏が提唱する「安田メソッド」を土台としています。
年齢ごとの育ちに合わせた運動遊びのねらい

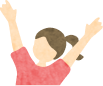
-
0・1 歳児
「感じる・つながる」経験を通して、心と体の土台を育む
-
2 歳児
「体を動かすって楽しい!」と感じる
-
3 歳児
「一緒にやってみたい!」という気持ちが育つ
-
4 歳児
憧れを力に変えて、工夫し乗り越える
-
5 歳児
仲間とともに挑戦し合う「燃える集団」に
具体的活動例や関わり、育まれる力は、お問い合わせまたは、園見学にて
運動遊びで育つ6つのチカラ
-
01
共感力
一緒にやってみたい
-
02
模倣力
まねして動く
-
03
観察力
よく見て気づく
-
04
発見力
どうしたら
うまくいくか考える -
05
判断力
自分で選び動く
-
06
対応力
状況に応じて
動きを変える
一人ひとりの「その子らしさ」を大切に
運動遊びは、「できるようになること」が目的ではありません。運動が得意な子も、ちょっぴり苦手な子も、それぞれのペースで楽しみながら、運動遊びを通して、体の使い方だけでなく、人との関わり方や、自分の感情との付き合い方も学んでいきます。


英語と文化の時間
耳と心がひらかれる幼児期に、ことばと世界を楽しむ
加茂川保育園では、英語を「早期教育」や「勉強」としてではなく、子どもたちの耳と心を豊かに育てる“ことばあそび”や“文化体験”として取り入れています。大切にしているのは、子どもたちが「聞いてみよう」「まねしてみたい」と感じ、自分から関わっていくこと。
無理に話さなくても大丈夫。安心できる雰囲気の中で、それぞれのペースで言葉や文化に触れ、自然に、楽しく英語や世界の文化に触れられる時間にしています。
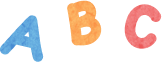
英語の“音”を楽しむことから始めよう!
英語には、たくさんの音やリズムがあります。この時期の子どもたちは、音を聞き分ける力や柔らかな感性をもっています。だからこそ、今しかできない「ことばや文化との出会い」を大切にしたいと考えています。
幼児期に、楽しく“音”に触れることで、特有の音の感覚や、耳や舌の作り方が自然と身についていきます。

幼児期だからこそ育つ「ことばのチカラ」
育みたいのは「ことばの力」や「表現する力」だけでなく、世界を知るおもしろさや、多様性を受け入れるやさしい心。加茂川保育園では、習い事の英語教育とは全く違い、一人ひとりの「知りたい」「言ってみたい」という気持ちを応援し、英語と文化を楽しむ時間としています。

※「英語と文化の時間」は、小・中・高の英語免許と保育士免許を持つ専門の職員が担当しています
具体的活動例や関わりは、お問い合わせまたは、園見学にて

加茂川保育園×食育活動
“食べること”から広がる
考える・感じる・つながる学び
加茂川保育園では、「食べること」を“命を育む”だけでなく、“考えるきっかけ”としてとらえ、探究的な食育活動にしたいと考えています。子どもたちの「なんで?」「どうして?」という小さな気づきや疑問を大切にしながら、日々の食の体験を豊かな学びへとつなげています。そして“今”できることを続けて、“先”を楽しみにできる。「育てて、待って、味わう」経験は、子どもたちの心の根っこを育てる大切な時間です。

「食べる」までの体験が、学びの宝庫
野菜の種をまき、水をあげ、育ちゆく姿を見守り、収穫し、調理して、食べる。
そのすべての過程に、子どもたちの「発見」があふれています。「なんでこのにんじんは短いの?」、「このトマト、まだかたいね」こうした素朴な疑問こそが、学びのはじまり。

体験から“問い”が生まれ、“問い”が学びになる
収穫の中で、「大きいのに小さいのより軽い野菜」に出会いました。すると、子どもたちの中から、「どうして中がスカスカなんだろう?」、「重いのと見た目は関係ないの?」といった気づきが生まれました。図鑑で調べたり、他の野菜と比べたり、重さを量ってみたり…。自然な流れの中で、観察・比較・考察・共有といった学びのプロセスが進んでいきます。また、「どんな野菜を育てたいか?」も子どもたちで選び、決める体験が、主体性と責任感を育てます

食べることが、“探究と成長の旅”になるように
加茂川保育園では、毎日の食事が子どもたちの「学び」と「育ち」につながる時間になるよう、「食べること」を通して、自ら考える力を育むこと。みんなで食べる幸せを感じる事。
それが、私たちの考える“食育”です。


ピコラボ
ICT × 子どもで育つ
「遊びからの学び」
加茂川保育園では、子どもたちの「なぜ?」「知りたい!」という気持ちを大切にしています。その探究心を支える取り組みが 「ピコラボ」です。
ピコラボは、iPadなどのICT機器を使い、日々の遊びや生活の中から「学び」へとつながるきっかけをつくる加茂川保育園独自の活動です。ICTを通して、子ども自身が気づき・考え・表現できるように寄り添うことを大切にしています。
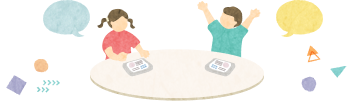
ピコラボの10の活動
-
01
調べる
-
02
世界見る
-
03
つながる
-
04
発見する
-
05
観察する
-
06
ふりかえる
-
07
時間を感じる
-
08
言葉をひらく
-
09
表現する
-
10
体験する
具体的活動内容や視点、育まれる力、どんなツールやアプリを使うのかなどは、
お問い合わせまたは、園見学にて
ピコラボの目的は「今知りたい」に応えること
ピコラボでは、ICT(タブレットなどの道具)は「目的」ではなく、子どもが自分から学ぶきっかけを広げるツールとして使います。「やってみたい」「知りたい」を、すぐに深められるようにサポートすることで、
子どもたちは “考え、表現し、つながる力”を身につけていきます。

























